山中城跡
西郷信貞が大永の初め(室町時代)に築城した三河地方最大規模の山城で、土濠土塁跡もよく保存されています。
標高204mの山頂には「山中城址」の碑が建ち、居館や曲輪跡から当時の山城のしくみを知ることができます。
標高204mの山頂には「山中城址」の碑が建ち、居館や曲輪跡から当時の山城のしくみを知ることができます。
三河地方最大規模の山城・山中城跡
山中城は岩尾山(医王山)の山頂にあり、愛知県内随一の広さを誇ります。
いつ、だれが築いたのか不明な点が多いですが、現在残る縄張は1,500年後半、戦国時代末期の家康公の改修によるものと考えられています。
城の境界に当たる場所には堀切を配置して尾根筋を遮断したうえで、曲輪斜面を横に伝って移動するのを防ぐために竪堀を備えることでより一層守りを固くしていました。
また、重要な出入口には馬出を配置しています。多方面からの敵の侵入を想定しながらも、進路を限定させて、守りやすく攻めにくい構造になっています。
随所に見られる細心かつ厳重な縄張は「土の城」の真骨頂とも言えます。
[縄張図の全体はこちらから]
画/七草
いつ、だれが築いたのか不明な点が多いですが、現在残る縄張は1,500年後半、戦国時代末期の家康公の改修によるものと考えられています。
城の境界に当たる場所には堀切を配置して尾根筋を遮断したうえで、曲輪斜面を横に伝って移動するのを防ぐために竪堀を備えることでより一層守りを固くしていました。
また、重要な出入口には馬出を配置しています。多方面からの敵の侵入を想定しながらも、進路を限定させて、守りやすく攻めにくい構造になっています。
随所に見られる細心かつ厳重な縄張は「土の城」の真骨頂とも言えます。
[縄張図の全体はこちらから]
画/七草
山中城跡の見どころ
竪堀
敵は曲輪の出入口(虎口)を正面から攻めてくるとは限りません。
曲輪のすぐ下の急な斜面を登ってくる敵もいます。そうした斜面を登ったり、横に移動してまわり込もうとする敵に対して、斜面の横方向へ移動するのを防ぐために竪堀が築かれました。
馬出
東曲輪の前面に位置し、北側と東側の侵入路の結節点に位置する半円形の小さな曲輪です。
敵は馬出を回り込まないと先へは進めませんが、馬出やさらに上の東曲輪にいる守備兵から弓矢や鉄砲を浴びるため侵入は極めて困難です。
小規模なため見落とされがちですが、とても重要な攻守の要です。
周辺スポット紹介
山中八幡宮
家康公の父・広忠公が再興したといわれ、家康公19歳の折、その後桶狭間の戦いへとつながる“大高城兵糧入”の際に必勝祈願に立ち寄られた神社です。
*鳩ヶ窟
三河一向一揆の際、一向衆に追われた家康公が境内の洞窟(鳩ヶ窟)に身を隠して難を逃れられたことから、尊崇した場所と云われます。
詳しくはこちら
マジカル
国道一号沿いにある、まちの洋菓子屋さんです。絵本から飛び出したような可愛らしい外観が特徴。イートインスペースがあり、モーニングやランチを楽しめます。
詳しくはこちら(マジカル公式サイト)
法蔵寺
家康公が幼少のころ、手習いや漢籍などの学問に励んだと伝えられる寺で、硯箱・硯石・手本・机・墨付小袖・破魔弓など家康公幼少期の品のほか、境内には六角堂開運勝利観音・東照権現宮・家康公ゆかりの草紙かけ松・おてならい井戸・お手植えの桜などの文化財も多く現存しています。
詳しくはこちら
道の駅藤川宿
岡崎市の東の玄関口に位置する、国道1号沿いの道の駅です。
岡崎の観光スポットや特産品紹介、新鮮な地元野菜の直売所や軽食が食べられるコーナーがあります。
詳しくはこちら
山中城跡と合わせて巡ってみよう
山中城跡へは、名鉄・名電山中駅から徒歩でアクセスでき、駐車場も整備されているため車でも訪れることができます。
さらに、11月にはアウトレットの開業も予定されており、あわせて楽しめるスポットが増えます。
周辺には家康公ゆかりの寺社や旧東海道も残されており、歴史散策にも最適です。
ぜひ一度、足を運んでみてください!
さらに、11月にはアウトレットの開業も予定されており、あわせて楽しめるスポットが増えます。
周辺には家康公ゆかりの寺社や旧東海道も残されており、歴史散策にも最適です。
ぜひ一度、足を運んでみてください!
- 山中城跡周遊コース①
- 山中城跡周遊コース② ※車で巡るコースです
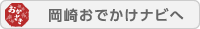
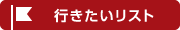

 岡崎ってこんなまち
岡崎ってこんなまち









