岡崎城跡(戦国時代)
岡崎城は、家康公が岡崎城を拠点としていたころと、関東に移った後とでは姿が異なります。
こちらのページでは、戦国時代末期の「土の城」であったときをご紹介します。
こちらのページでは、戦国時代末期の「土の城」であったときをご紹介します。
土の城・岡崎城
このイラストは、家康公が関東移封になる以前(戦国末期)の「土の城・岡崎城」を復元したものです。
岡崎城は1450年頃、西郷氏が初めて砦を築き、1530年頃に家康公の祖父・松平清康が城主になって以降、松平・徳川氏の本拠の城として発展していきました。
城は乙川(菅生川)に張り出した台地の先端を利用して築かれています。
本丸から北東方向は台地が地続きとなることから、幾重にも空堀を掘ることで防衛線としました。本丸・二の丸・東曲輪が主要な曲輪であり、それぞれの侵入路に攻守の要である馬出を配置したつくりとしました。
さらに岡崎城の北東には馬出を備えた「新城」があり、東側の低地部からの侵入にも備えていました。
三河・浜松時代の家康公は今川氏、武田氏との戦いの中から最先端の築城術を学び、取り入れながら自分のものとして「家康の城」を確立していきました。
その到達点が「土の城・岡崎城」であり、その前身が日近城、山中城、岩津城に他なりません。
[縄張図の全体はこちらから]
画/松岡徹
岡崎城は1450年頃、西郷氏が初めて砦を築き、1530年頃に家康公の祖父・松平清康が城主になって以降、松平・徳川氏の本拠の城として発展していきました。
城は乙川(菅生川)に張り出した台地の先端を利用して築かれています。
本丸から北東方向は台地が地続きとなることから、幾重にも空堀を掘ることで防衛線としました。本丸・二の丸・東曲輪が主要な曲輪であり、それぞれの侵入路に攻守の要である馬出を配置したつくりとしました。
さらに岡崎城の北東には馬出を備えた「新城」があり、東側の低地部からの侵入にも備えていました。
三河・浜松時代の家康公は今川氏、武田氏との戦いの中から最先端の築城術を学び、取り入れながら自分のものとして「家康の城」を確立していきました。
その到達点が「土の城・岡崎城」であり、その前身が日近城、山中城、岩津城に他なりません。
[縄張図の全体はこちらから]
画/松岡徹
岡崎城跡の見どころ(戦国時代)
清海堀(せいかいぼり)
岡崎城の最初の築城者・西郷頼嗣の法名「清海入道」から名付けられた空堀で、主に本丸北側の堀のことを指します。
本丸土塁から堀底まで10m以上の深さがあり城内でも最大級の規模を誇ります。
本丸土塁から堀底まで10m以上の深さがあり城内でも最大級の規模を誇ります。
周辺スポット紹介
菅生神社
岡崎最古の神社、日本武尊命により(西暦110年)創建。
御祭神は、天照皇大神・豊受姫命・須佐之男命・徳川家康公・菅原道真公をお祀りしています。
松平家・徳川家康公ゆかりの神社で家康公が25歳の時、厄除開運祈願をされ、社殿・寄進田など厚く崇敬されていました。
詳しくはこちら
八丁味噌蔵
岡崎は、古くから豆味噌の産地として知られていました。矢作地域の大豆や三河湾の塩でつくられる味噌は、保存食として優れ、戦国時代には三河武士の兵糧としても重宝されました。家康公も豆味噌を食していたといわれています。
市内には「まるや八丁味噌」「カクキュー八丁味噌」の2件の味噌蔵があり、昔ながらの伝統製法で八丁味噌を造り続けています。
詳しくはこちら
大正庵釜春本店
釜揚げうどんの元祖として有名な老舗店。
もちもちとした麺は特注の粉で作る手打ち麺で、こだわりのつゆは門外不出の味です。
詳しくはこちら
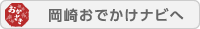
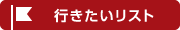

 岡崎ってこんなまち
岡崎ってこんなまち






