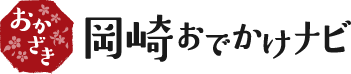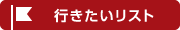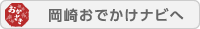岡崎城(江戸時代)
「土の城」であった岡崎城が天守や櫓、石垣がそびえる城へと変化したのは、1590年に家康公が関東に転出し、新たに豊臣武将・田中吉政が城主となってからのことです。
石垣の城の出発点・岡崎城(江戸時代)
田中吉政は岡崎城を大改修し、戦国時代の「新城」を岡崎城に取り込んで備前曲輪とし、馬出に大手門を配置し(後に浄瑠璃曲輪に移動)、さらに城下町の外郭を堀(総堀)で囲い込んで巨大な城としました。
城の規模もさることながら、石垣が多用され、瓦葦の天守や櫓が建てられたことで城の景観は一新されました。また、城下に東海道を引き入れ、くねくねとした屈折の多い街道筋は、「東海道二十七曲り」と呼ばれました。
城下の防衛とともに、街道筋に多くの店舗が立ち並ぶことができ、経済効果も考えられたつくりとなっています。岡崎城はこの地域における「土の城」の到達点であり、同時に本格的な「石垣の城」の出発点となりました。
現在の岡崎城公園に江戸時代の建物はありませんが、石垣は当時のまま残っています。
ぜひ、石垣めぐりも楽しんでみてください。
[縄張図全体はこちらから]
画/松岡徹
城の規模もさることながら、石垣が多用され、瓦葦の天守や櫓が建てられたことで城の景観は一新されました。また、城下に東海道を引き入れ、くねくねとした屈折の多い街道筋は、「東海道二十七曲り」と呼ばれました。
城下の防衛とともに、街道筋に多くの店舗が立ち並ぶことができ、経済効果も考えられたつくりとなっています。岡崎城はこの地域における「土の城」の到達点であり、同時に本格的な「石垣の城」の出発点となりました。
現在の岡崎城公園に江戸時代の建物はありませんが、石垣は当時のまま残っています。
ぜひ、石垣めぐりも楽しんでみてください。
[縄張図全体はこちらから]
画/松岡徹
岡崎城の見どころ(江戸時代)
岡崎城の周辺では、石垣を築くのに適した花崗岩が豊富に産出しました。
最も古い石垣は石材を山からそのまま運んできて積み上げた「野面積み(のづらづみ)」ですが、次第に石材を適度な形に割って積む「割石積み(わりいしづみ)」や、割石をさらに加工した「切石積み(きりいしづみ)」へと発展していきます。
石垣の発展過程を知ることができるのも岡崎城の大きな魅力の一つです。
石垣づくりがひと段落した1600年代後半には石灯籠などの石工業が盛んとなり「石都(せきと)岡崎」と呼ばれるようになりました。
「岡崎城跡石垣めぐり」パンフレットはこちら
「石都・岡崎!」特集ページはこちら
最も古い石垣は石材を山からそのまま運んできて積み上げた「野面積み(のづらづみ)」ですが、次第に石材を適度な形に割って積む「割石積み(わりいしづみ)」や、割石をさらに加工した「切石積み(きりいしづみ)」へと発展していきます。
石垣の発展過程を知ることができるのも岡崎城の大きな魅力の一つです。
石垣づくりがひと段落した1600年代後半には石灯籠などの石工業が盛んとなり「石都(せきと)岡崎」と呼ばれるようになりました。
「岡崎城跡石垣めぐり」パンフレットはこちら
「石都・岡崎!」特集ページはこちら